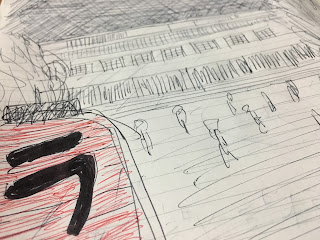こう書くと奇異の念を抱く人もいるかも知れないが、僕が西武池袋線沿線に住んでいた頃は、練馬区中村北にあるこの立体交差は上下が逆だったのである。
2001年3月にこの入れ替え工事が行われた時には、僕は既に品川区に引っ越していたが、幹線道路の通行を迂回路に回しておき、鉄道の終電後の工事で場所をそっくり入れ替えて、どちらも次の朝から運用を再開させるという、長期間に渡る綿密な準備の末に行われたこの手品の様な一夜の大工事は、当日のニュースで大きく報道され、工事の完結を見る事無く引っ越してしまった僕も、その様子を垣間見る事が出来た。
僕がこの辺りに住み始めた当初、西武池袋線はまだ高架上ではなく地上を走っていて、駅の東側を通る中杉通りにあった踏切りは、朝夕の通過電車の多い時間帯は上下線合わせて7本通過しないと開かなかった。そして大抵の場合、7本目は無人の回送電車だったので、余計にイライラしたものである。
その後数年して、線路を高架にする為の工事が始まり、駅は囲いで覆われて足場が組まれ、そこかしこに工事用の資材が並べられた。
そして先ず上り線が高架上を走る様になり、それだけで踏切が開かない時間は激減した。作業場や工事現場の様な雰囲気が好きな僕は当時、『この状態で工事が終わったら面白いな』などと思ったものである。
やがて駅の工事は完了し、中村橋駅は上下線とも高架上を電車が走るようになった。
駅は高架になる前から上下線のホームが別々で、双方を結ぶ地下道や跨線橋の類は無かった。その為、中杉通りの北の終点近くに住んでいた僕は、下り線で池袋から帰って来て改札を出ると、工事前は電車の通過が済むまで踏切で待たなくてはならなかったのだが、工事後はそのまま高架を潜って行ける様になった。
しかし僕にとって何よりも嬉しかったのは、高架上を電車が動き出す時の重く規則正しい振動音を、地元の駅でいつでも聞ける様になったという事であった。
ところで、「中杉通り」という名称は、僕は中村橋と杉並を結んでいるから付けられたものだとずっと思っていたのだが、実は中野と杉並を結んでいる為というのがどうやら定説らしい。当時の僕は、阿佐ヶ谷以南にも中杉通りが続いている事など、全く考えが及ばなかったのである。
それはともかく、この通りは阿佐ヶ谷駅から西武新宿線の鷺ノ宮駅を経て、中村橋駅の手前で千川通りと交差するまでは道幅が広く、交通量の多い道路なのだが、その先からは一方通行になって急に道幅が狭まり、駅の北側に出ると、地元の商店街へと風景が一変してしまう。そして、その賑わいが途絶え、少し寂しさを覚える様な界隈を通り過ぎると、突然、だだっ広い目白通りにぶつかり、そこが終点となる。
その中杉通りの中村橋駅と阿佐ヶ谷駅の間の一本道を路線バスが通っていて、よくそれに乗って阿佐ヶ谷まで行き、ホープ軒でラーメンを食べて帰って来たものである。
或いは、当時勤めていた会社があった江東区の門前仲町から、総武線乗り入れの車両を選んで東西線に乗り、阿佐ヶ谷で一杯食べてからバスで中村橋まで帰るという、かなり長距離の寄り道をする事もたまにあった。
阿佐ヶ谷のホープ軒を知ったのは、第一話で書いた通り、千駄ヶ谷のホープ軒の話をした時に友人が見せてくれた当時のチラシでだったが、なるほど阿佐ヶ谷と千駄ヶ谷ではラーメンの雰囲気が全く違っていて、阿佐ヶ谷の方はスタンダードで食べやすい、昔ながらの中華そばという感じだったと記憶している。
店内には、日本の懐メロかグループサウンズ風の音楽が流れ、幾分小ぶりの丼から、シンプルでいて、しかし十分にコクのある豚骨醤油スープが絡んだ麺を啜り上げて食べていた記憶があるのだが、一昨年、東京に行く機会があって久々に訪ねた時は、ラーメンそのものだけでなく、店全体の印象が当時の記憶とは全く違っていた。
阿佐ヶ谷にはホープ軒以外の目的で行った事は無いので、店は間違い様が無いのだが、これだけ印象が違うというのはどういう事だろうか。単に僕の記憶が、その後の様々な体験によって上書きされてしまったという事なのだろうか。
自分ではしっかりと記憶していると思っていても、人間の記憶とはかなりあてにならないものであるという事を、改めて思い知らされたものである。
その中村橋と阿佐ヶ谷を結ぶバスの、中村橋側の終点の辺りに昔、小さなラーメン屋があった。87〜8年ぐらいの事で、名前はもう憶えていない。
初めてその店に入ったのは、たまには地元の町で一日のんびりと過ごしてみようと考えたある休日だった。
翌週の為の食料の買い出しを西友で済ませて千川通りに出たところで、ちょうど通りの反対側にある、その店の暖簾が目に留まったのである。見るからに地元の食堂然とした外観が、昼からビールでも飲んでラーメンを啜ろうと思っていた僕の気分にぴったり合っている様な気がした。
短い暖簾を潜り、古い引き戸を開けて中に入ると、外観から抱くイメージ通り、昔ながらの食堂そのものといった雰囲気の店内にはテーブルがいくつか並べられ、老夫婦が協力し合って調理と客の案内をこなしていた。
地味で古臭いながらも、良く整頓されていて無駄なものが無く、簡素で落ち着いた雰囲気が、店を切り盛りする老夫婦をそのまま写した様な佇まいである。
数組の先客がそれぞれのテーブルを占める中、一人客の僕も店主のおじいさんの案内に従い、空いているテーブル席に着いた。
メニューもまた単純明快。ラーメンと上ラーメン、加えて、それぞれの大盛りだけである。
そして、メニューを見て僕が発した一言が良くなかった。
「ビールは無いんですか?」
「そんなもん無いよ」
おじいさんの反応には、ビールを飲みながらラーメンを食べるという行為に対するあからさまな軽侮の念があり、鼻で笑うようなニュアンスを感じ取った僕は面喰ってしまった。
取り敢えず「上ラーメンの大盛り」を注文して待つ間も、『休日に地元で昼から一杯ひっかけるのは気分が良いだろうと思って入ったのに、どうして、よりによってこんなへんつくなおやじの店を選んでしまったのだろう』という後悔の念でいっぱいだった。
暫く待った後、今度はおばあちゃんがお盆に乗せて運んできたラーメンを見て、驚いた。白い丼に張られた幾分黄色味掛かった透明なスープに、肉団子と白ネギが浮かべられたその簡素なラーメンは、今までに見た事もない様な淡い色彩と、香ばしく甘い匂いに包まれていたのである。
そして、その良い匂いを発している綺麗なスープをレンゲで啜り、麺が唇を通過していく心地よい感触を味わっているうちに、ビールを飲みながらこのラーメンを食べようとしていた自分が甚だ愚かしく思えてきた。こんな繊細なものを味わうのに、アルコールの刺激と酔いは邪魔でしかない。
僕がそれまで好んで食べていたラーメンは、こってりしていてボリュームがあり、何よりもチャーシューが旨いのが条件だった。それほどラーメンばかりを食べ歩いていたわけではないが、ラーメンを食べるならチャーシューが旨くて腹いっぱいになるのが良いという様な、偏った嗜好を持っていたのである。
しかし、目の前にあるラーメンは、紛れもなく僕の好みとは真逆の代物で、量は大盛りでそこそこあるが、透き通ったスープに、チャーシューではなく肉団子が乗っている。
最初は戸惑ったが、一口啜ってみると麺を掬う箸が止まらなくなり、見た目でがっかりさせられた肉団子も、涎が口から溢れ出てしまうぐらい旨味に溢れていたのである。
スープにはおそらく鶏ガラと野菜、煮干しなどが使われ、濁りを出さない様に丹念に炊かれていたと思われる。少し縮れた細い麺に絡んで口の中に入って来る、その透明な液体を舌の上に留めて味わい、噛み砕いた麺と共に飲み下す時の心地良さは、このひと時は他の事に捕らわれず、一心に味わう事を要求している様に思えた。
 感動のひと時が静かに終わりを告げ、その余韻に暫く浸った後で、その店に漂う雰囲気にすっかり感化された様にゆっくりと支払いを済ませ、静かに引き戸を開け、僕は千川通りの明るい歩道に戻った。
感動のひと時が静かに終わりを告げ、その余韻に暫く浸った後で、その店に漂う雰囲気にすっかり感化された様にゆっくりと支払いを済ませ、静かに引き戸を開け、僕は千川通りの明るい歩道に戻った。この時の事は今でも僕の心に強い印象を残していて、透き通った端正なラーメンに出会うと必ず、この店のラーメンが頭に浮かんで来る。
別に、比べてどちらが優れているかという事ではない。おそらく、かなり美化されているであろう僕の記憶の中の一杯と、現実のそれを比べる事など何の意味もありはしないのだが、ただ一瞬だけ、この店のラーメンを思い出し、懐かしい想いに触れたくなるのである。
この店にはその後数回行き、毎回「上ラーメンの大盛り」を食べていたが、暫くすると、店の前を通り掛かっても開いていない事が多くなっていった。
その当時の僕の自宅は、中杉通りの終点である目白通りとの交差点を真っ直ぐに抜け、その奥に続く八百屋と魚屋と酒屋だけの小さな商店街の先にあるアパートの一室だった。そこから目白通りまで戻った所の角に建っているマンションの地下に、当時たまに顔を出していたShimaという小さなスナックがあり、その店の常連にラーメン好きの人がいて、そのラーメン屋の事を聞いてみた事がある。
「あの店は、昼時は満席になるくらい人気があるから、心配しなくても無くなる事はないよ」
と、その人に言われて安心していたのだが、そのまま店が開いているのを見る事は無く、いつの間にかそこにラーメン屋があったという痕跡さえも消え、年月が経つと共に、僕の頭の中からも確たる記憶が失われてしまった。
僕は、何度も通った店でも気軽に店の人と会話を交わす様な社交的な性格では無かったので、あの老夫婦にどんな事情があったのかは、遂に知る事が出来なかった。おそらく、歳を取ったので区切りをつけたのだとは思うが、これが最後と分かって食べる一杯を味わえなかったのが、今でも心残りである。
中村橋での生活は、ちょうど10年間に及んだ。その前に1年ほど、隣の富士見台にも住んでいたので、練馬区内で11年以上も暮らした事になる訳だが、その間、西武池袋線は高架になり、地下鉄が乗り入れ、富士見台にいた頃に住んでいたアパートのすぐ近くに練馬高野台駅が出来た。
中村橋を去ってから20年以上の時が過ぎた一昨年、千駄ヶ谷と阿佐ヶ谷のホープ軒で続けてラーメンを食べた後、あの頃と同じ様に中村橋行きのバスに乗り、懐かしい街を訪ねてみた。
中村橋に降り立つと、まず周囲の街並みの変化に驚かされた。
高架下に綺麗なショッピングモールができ、当時は千川通りから三井住友銀行の手前の路地を入って行っていた西友が、駅と直結している。千川通り沿いでわずかに記憶に残っていたモスバーガーも今は無く、この付近で全く変わっていないと感じたのは、角の蕎麦屋と、まだ富士見台にいた頃に痛ましい事件のあった交番ぐらいであった。
中村橋商店街に入る前に、千川通りを西に歩いて富士見台に行ってみた。こちらも中村橋同様、高架下が新しい商業施設になり、駅前はかなり様変わりしていたが、石神井方面に向かって商店街を歩いていくと、以前とそれ程変わっていない事に気付かされた。
途中、「味の横綱」という、僕が住んでいた頃はまだ出来て間もなかった店が、見事に年季の入った町の中華食堂になっていた事に、懐かしさと共に堪らない喜びを感じ、入ってみた。そこで久しぶりにタンメンを食べながら店主と少しだけ当時の話をし、その後、中村橋に戻ってのんびりと商店街を散策して、真ん中辺りにある居酒屋で、また懐かしさに浸りながら夕食を摂った。
帰路は、西武池袋線の上り電車で池袋に向かう。
電車が動き出して間も無く、立体交差で目白通りが上を通っていた頃、散歩中に豊島園のフライングパイレーツが揺れているのが遠く眺められた事を思い出し、電車の窓から覗いてみたのだが、既に日はだいぶ傾き、過ぎし日の懐かしい景色をこの目に収める事は叶わなかったのである。
第三話・完
ランキングに参加しています。こちらをクリックしていただけると有難いです。
↓

ラーメンランキング

エッセイ・随筆ランキング